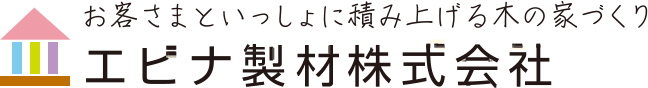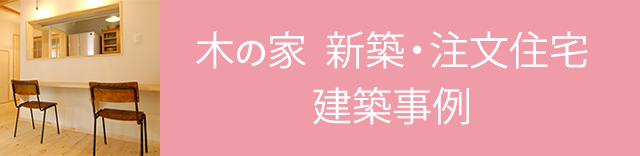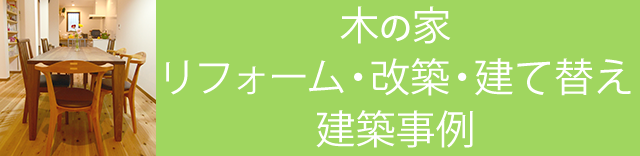京都市右京区M様邸の新築木の家注文住宅工事経過
2024年3月に初めてお会いして、打ち合わせを1年程かけて工事着工となりました。お子さんが独立して子育てが終わった50代のご夫婦2人の木の家をつくります。京都市右京区M様の木の家は建て替えになります。
2025年10月4日・5日 完成見学会を開催しました









10月4日と5日の2日間、M様邸にて完成見学会を開催しました。
前日に打設したばかりのコンクリートにキズがつかないよう、しっかり養生を行いながらの開催です。
これまでに資料請求をいただいた方々へご案内をお送りし、完全予約制で1組ずつご案内しました。
■ 狭小地で床面積を最大限に活かす工夫
M様邸の大きな特徴は、「45分準耐火構造」とすることで建ぺい率を10%増やせる点です。
この構造を採用することで、限られた敷地の中でも1階部分をより広く確保することができます。
ただしその分、木構造部分はすべて強化石膏ボードで被覆する必要があり、
いつものように梁や柱を見せるデザインはできません。
天井高さはできるだけ開放感を出すために2,500mmを確保し、
床には無垢材を使用して温かみを感じられる空間に仕上げています。
■ ご来場いただいた皆さま
見学会には、すでに打ち合わせが進んでいるお客様や、
「どんな家が建つのか実物を見たい」という方々にお越しいただきました。
実際にご覧いただくことで、狭小地での家づくりの工夫や、
構造とデザインのバランスをどう取っているのかを感じていただけたようです。
今回のM様邸は、敷地条件を最大限に活かした設計と、確かな施工技術によって
「小さくても心地よい住まい」を実現しています。
2025年10月3日 外構の土間コンクリート打設と防草対策
外構の土間コンクリート打設を行いました。
両サイドの通路部分は防草シートを敷き、その上に砕石を敷いて仕上げています。
通常、外構工事は専門の外構業者さんをご紹介することが多いのですが、
今回はコンクリート打設の面積が比較的小さく、特殊な仕様もなかったため、
エビナ製材で施工させていただきました。
打設前には、既存のコンクリートブロック塀に残っていたバリ(余分な突起)を丁寧に取り除き、
仕上がりがきれいになるように下準備をしています。
シンプルながらも、見た目にも清潔感があり、メンテナンスしやすい外構に仕上がりました。
暮らし始めてからの使いやすさも考慮した、実用的で丁寧な仕上げです。
2025年9月30日 内装工事が完了し、完了検査に合格しました
内装工事がすべて完了しました。
床を保護していた養生材を剥がし、ハウスクリーニングを行って、ようやく完成目前の姿に。
これまで現場で積み重ねてきた作業の成果が一気に姿を現しました。
完了検査にも無事合格し、これでいよいよお引っ越しの準備に入れる段階となりました。
白い壁と木の質感が調和した、明るく心地よい空間に仕上がっています。
2025年9月20日 設備機器の取付が完了しました

9月20日、京都市M様邸の設備機器の取付工事が完了しました。
キッチンの設置を終え、外部では足場を撤去。
これにより建物の全体像がようやく姿を現しました。
室内では洗面化粧台やトイレの便器、紙巻器、タオル掛けなどの取付も完了しています。
また、給水・給湯・排水管の接続工事に加えて、電気の引き込みも完了しました。
照明器具が点くようになり、室内が一気に明るくなったことで、完成の姿がよりはっきりと感じられるようになりました。
職人さんたちの丁寧な仕上げによって、生活のイメージが少しずつ形になっていく――
そんな現場の“完成に向かう高揚感”が漂うタイミングです。
2025年9月4日~8日 クロス工事が進んでいます


9月4日から8日にかけて、京都市M様邸のクロス工事を行いました。
大工さんが丁寧につくり上げた壁や天井の下地に、クロス(壁紙)を貼っていきます。
キッチン・洗面所・トイレの床には、耐水性のあるクッションフロアを施工しました。
それぞれの空間に合わせた素材を使い分けることで、見た目だけでなく使い心地やお手入れのしやすさも考えています。
これまで下地の強化石膏ボードの色だった薄いグレーベージュの壁や天井が、
白いクロスに変わったことで、室内全体がぐっと明るく感じられるようになりました。
光が反射して、空間に広がりを感じる気持ちの良い仕上がりです。
2025年8月29日 木工事が終わりました!


約2ヶ月かけて、大工さんによる木工事がひと段落しました。
壁や天井には石こうボードが貼られて、家の形がぐっと見えてきています。
打ち合わせで一緒に考えた可動棚やニッチも取り付けられていて、実際に形になると「ここにこんな工夫をしたんだな」とイメージがはっきりしてきました。
ここからは仕上げの工事に進みます。
クロスやクッションフロアを貼ったり、キッチンやトイレを設置したりして、いよいよ住まいとしての完成が近づいてきます。
打ち合わせが形になったオリジナルの棚や収納
石こうボードで家らしい空間に
このあとは内装と設備工事で一気に完成に近づきます
クロスが貼られると部屋の雰囲気がガラッと変わって、一段と楽しみになってきます。
2025年8月8日 アイシネン吹付断熱工事完了、石膏ボード貼りへ
7月28日・29日・30日の3日間で、アイシネン吹付断熱工事が完了しました。
現在は引き続き、内装下地づくりを進めています。石膏ボードを貼る前に必要な下地を仕込み、その後ボードを一枚ずつ丁寧に貼っていきます。
石膏ボードが貼り終わると、階段の設置や枕棚・棚柱の取り付け、可動棚の設置など、内装工事がさらに進んでいきます。
2025年7月3日 現場にスポットクーラーを設置しました
壁と天井の下地をつくり、サッシも取り付けて、ようやく建物の内と外がはっきり区切られました。現場にはスポットクーラーを入れてはいるのですが、やはりこの暑さではなかなか涼しくならず、作業効率も落ち気味です。
本格的に快適に作業できるようになるのは、建物全体に断熱材(アイシネン吹付断熱)の工事が終わってからになりそうです。
このあと進んでいく工程としては、スイッチ・コンセント・照明器具の設置に向けての電気配線工事、お客さまに選んでいただいたシステムキッチン・システムバス・洗面台・トイレの承認図をもとに、水道とガスの配管工事を行っていく予定です。
2025年6月17日 上棟を行いました

当日は道路幅が狭い場所のため、資材の搬入やレッカー車の設置に伴い、一時通行止めとさせていただき、無事に作業を終えることができました。
梅雨の晴れ間で最高気温35度という厳しい暑さのなか、大工さんをはじめ関係する職人の皆さんが力を合わせ、無事に上棟の日を迎えられたことに感謝いたします。
M様、このたびは上棟、誠におめでとうございます。今後も安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
2025年6月13日、土台据えを行いました

この日から大工さんが現場に入り、基礎の上に「土台」と「大引」と呼ばれる木材をしっかり固定していきます。基礎の上にはまず20mm厚のパッキンを置き、その上に木材を設置することで、通気性を確保し、湿気による劣化を防ぐ工夫をしています。
エビナ製材では、土台や大引にはシロアリや腐れに強い国産ヒノキの無垢材を使用。さらに防蟻処理も施しますが、万が一薬剤の効果が薄れても、もともと丈夫な木材を選ぶことで、長く安心して暮らせる家づくりを大切にしています。
2025年6月9日、基礎工事が完了し、そのあと水道管の配管工事も終わりました
現代の工事では、給水・給湯用の水道管と排水管を基礎の上に通す方法を採用するのが一般的です。
昔は地中に埋めてしまうことが多かったのですが、今は将来、数十年後に水道管やガス管の取り替えが必要になったとき、できるだけ簡単に交換できるよう、基礎の上に配管するのが一般的になっています。
これで次の工程、土台据え・上棟の準備が整いました。
2025年5月28日、基礎の「ベースコンクリート」の打設が完了しました

これは、基礎の一番下の部分にあたるコンクリートを流し込む作業で、建物をしっかり支える土台になります。
コンクリートは打ちたてのときは濃いグレーをしていますが、時間が経って乾いてくると、だんだんと明るいホワイトグレーに変わっていきます。
この後は、基礎の立ち上がり部分(壁のように立ち上がる部分)のコンクリートを打設していきます。
2025年5月24日、住宅の基礎に使う鉄筋(配筋)の組み立てが完了しました
基礎のコンクリートの中に入る鉄筋は、建物をしっかり支える大切な部分です。この工程では、図面通りの位置に鉄筋を並べ、しっかりと固定していきます。
鉄筋の太さや間隔は、建物の構造に合わせて細かく決められていて図面で指示しています。完成後はコンクリートの中に隠れてしまう部分ですが、とても重要な工程です。このあと、第三者機関による配筋検査を受け、問題がないことを確認したうえで、いよいよコンクリート打設へと進みます。
2025年5月19日、住宅の基礎工事の一工程である「捨てコンクリート」の打設が完了しました
捨てコンクリートは基礎をつくるための下地となるもので、まず土を掘削し、防湿用のシートを敷いたあと、その上に薄くコンクリートを打つ作業です。
この捨てコンクリートの上に、建物の正確な位置や壁のラインを墨で印していくことで、「どこにどの部屋ができるのか」「部屋の広さはどれくらいか」が、図面だけでなく実際の現場でもイメージできるようになってきます。
2025年3月24日 既存建物解体完了

全面の道路幅が狭いため解体した廃棄物を積み込むためのトラックを一時的にも置いておくことが難しかったこと等もあり、通常より少し時間がかかりましたがキレイに更地になりました。
解体のあと現場のほうで実際の敷地形状を図面に落とし込めるようにするため、座標点のある測量に入ってもらっています。その座標をパソコンで入力して図面に反映させて、建物を敷地上のどの位置に建てるかを検討して決めていきます。
昔の測量図が法務局にある場合でも、今のように座標点をとって完全に敷地形状を把握できるものではなく、面積を測れさえすればOKな時代の測量図なのであてにならないため、仮測量は必要です。
2025年3月3日 既存建物解体着工

築50年経過したこちらのお住まいを解体して建て替えます。
事前に電気メーター取外し、下の写真のようにガス管の側溝カットを手配しておいて、解体作業に危険がないようにしておきます。水道は解体していくとホコリが舞うので散水のため使用します。

2025年3月29日 12:19 PM
ブログメニュー:京都市右京区M様の木の家 │コメント(0)